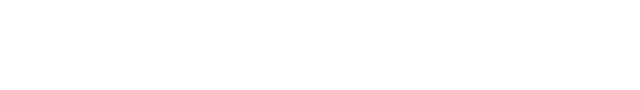糖尿病の診断基準
[2025.06.26]
糖尿病の診断基準(日本糖尿病学会 2024年版に準拠)は以下の通りです。診断には原則として別の日に行った2回以上の検査での確認が必要ですが、重症例などでは即日診断されることもあります。
■ 糖尿病の診断基準(いずれかを満たす)
① 空腹時血糖値(FPG)
126 mg/dL以上
-
検査前10時間以上絶食した状態での血糖値。
② 75g経口ブドウ糖負荷試験(75g OGTT)
2時間値:200 mg/dL以上
-
通常、初回検査で糖尿病型かどうかを判断。
-
経口ブドウ糖投与後の2時間後の血糖値を測定。
③ 随時血糖値
200 mg/dL以上
-
食後・時間帯を問わず測定した血糖値。
④ HbA1c(NGSP値)
6.5%以上
-
過去1〜2か月の平均血糖を反映。
-
血糖値だけでなく、HbA1cも診断の補助指標として重要。
■ 診断の流れ(原則)
| パターン | 診断方針 |
|---|---|
| 血糖値(①〜③のいずれか)+HbA1c 両方が糖尿病型 | 原則として糖尿病と診断可能 |
| 血糖値のみ糖尿病型、HbA1cが6.5%未満 | 別日に同様の血糖検査で再検査 |
| HbA1cのみ6.5%以上、血糖値が正常または境界型 | 別日に血糖検査を実施し、再確認 |
■ 特別な状況
-
糖尿病の典型症状(口渇、多尿、体重減少など)+随時血糖200 mg/dL以上 → 即日診断可能。
-
糖尿病性ケトアシドーシスや高浸透圧高血糖症候群など → 緊急対応と同時に糖尿病と診断。
■ 注意点
-
HbA1c値は貧血・腎疾患・肝疾患・妊娠などで正確でないことがあります。
-
診断が確定した後は、治療・教育入院や生活指導が行われます。